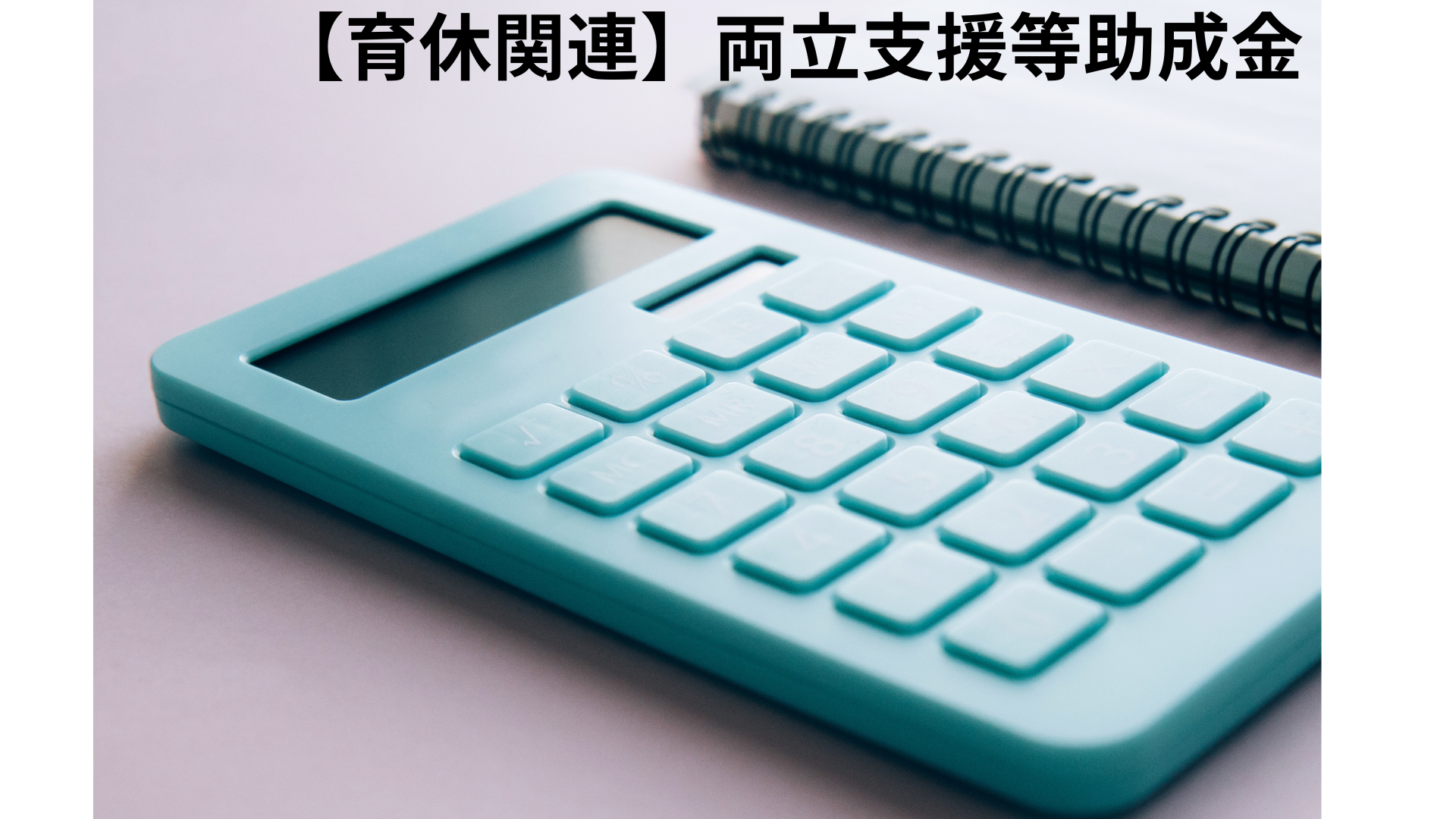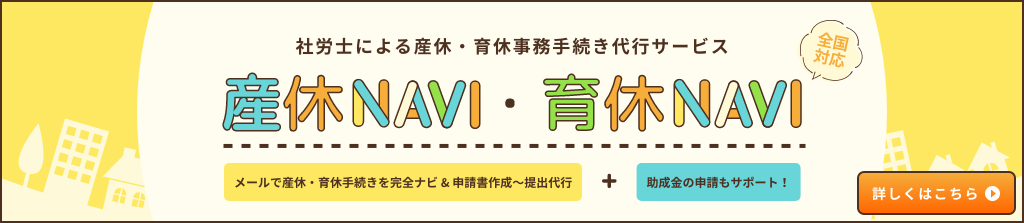この記事では、今後の育児休業等に関する、その他法改正情報について解説しています。
子が3歳になるまでのテレワーク推進 努力義務化(令和7年4月1日 施行)
3歳になるまでの子を養育する従業員に対し・・・
☑
テレワークの活用を推進すること
☑
育児短時間勤務制度の適用が難しい業務に従事する労働者に対して、代替としてテレワークの活用を推進すること
が事業主の努力義務となります。
育児短時間勤務制度の拡充および代替措置の追加(令和7年10月1日 施行)
現在、「育児短時間勤務制度」については、「1日6時間の勤務制度」を定めておくことのみが義務化されておりますが、「1日6時間の勤務制度」のみならず「他の勤務時間による制度」もあわせて設定することが望ましいとの指針が示されることとなりました。
また、労使協定で「時短措置が困難な業務」として、育児短時間勤務制度の適用から除外した労働者に対し、現状、義務化されている以下の代替措置(いずれかの措置を選択して導入)の選択肢にテレワークを追加することが義務化されました。
現状、義務化されている選択肢(以下いずれかの制度を代替措置として導入)
- フレックスタイム制度を導入する
- 時差出勤制度を制定し、始業・終業時刻の繰上げ、繰下げを行う
- 育休に準ずる制度を定め、子が3歳になるまで休業させる
- 事業所内保育施設を設置運営する
- 保育施設利用料の補助を行うなど、事業所保育施設運営に準ずるような便宜の供与を行う
上記にプラスして「テレワークの導入」を選択肢に加えることが義務化されます。
仕事と育児の両立に関する個別の意向確認・配慮の義務化(令和7年10月1日施行)
全ての事業主に対して、
現行は・・・
「本人または配偶者が妊娠・出産したこと等を申出した労働者」へ「育児休業の取得を希望するか否かについて」の意向を確認することが義務付けられています。
改正法施行後は・・・
☐本人又は配偶者が妊娠・出産したこと等を申出した労働者
に対してのみでなく
☐3歳に満たない子を養育する労働者
にまで対象範囲を拡大し
以下について、追加で確認すべきことが義務化されました。
子や家庭の状況により仕事と子育ての両立が困難な状況にある場合、その支障となる事情の改善に資するものとして・・・
- 勤務時間帯
- 勤務地にかかる配置
- 業務量の調整
- 両立支援制度の利用期間等の見直し
- 労働条件の見直し
等についての希望内容を確認すべきこと。
また、「事業主が、上記の労働者の就業条件を定めるにあたり、確認した意向(希望内容)に配慮しなければならないこと」についても義務化されることとなりました。
さらに、望ましい対応として・・・
☐子に障害がある場合等で希望するときは、短時間勤務制度や子の看護等休暇等の利用可能期間を延長すること
☐ひとり親家庭の場合で希望するときは、子の看護等休暇の付与日数に配慮すること
も指針として示されています。
3歳以降小学校就学前までの「柔軟な働き方を実現するための措置」義務化(令和7年10月1日施行)
3歳以降小学校就学前までの子を養育する労働者に対する両立支援制度として・・・
- 始業時刻等の変更(フレックスタイム制・時差出勤制度の導入等による)
- テレワーク等(*)(月あたり10日以上、時間単位での実施も可とするもの)
- 短時間勤務制度
- 新たな休暇の付与(年10日以上、時間単位での取得も可とするもの)
- 保育施設の設置・運営その他これに準ずる便宜の供与
(*)
テレワークを措置として実施する場合は、「労働時間の適切な把握等」を行うことにより「心身の健康に配慮」すべき旨、指針が示されています。
の中から2以上の措置を実施することが事業主に義務付けられます。
なお、上記の措置を実施するにあたっては、あらかじめ過半数労働者代表(または過半数労働組合)の意見を聴かなければならないこととされています。
また、上記の措置を実施した場合、従業員はその中から1つの制度を選択して利用できることとなっています。
「柔軟な働き方を実現するための措置」の個別周知・意向確認 義務化(令和7年10月1日施行)
前節で解説の、3歳以降小学校就学前までの「柔軟な働き方を実現するための措置」の実施が事業主に義務付けられるにあたり、子を養育する労働者に対して、3歳になるまでの適切な時期に面談等の措置を行い・・・
☐あらかじめ定められた2以上の措置に関する情報を個別に周知すること
☐上記の措置利用についての意向について事前確認を行うこと
についても、あわせて事業主に義務付けられることとなりました。
上記、面談等については、1回のみでなく「柔軟な働き方を実現するための措置」利用期間中等に定期的に行うことが望ましいとの指針が示されています。
それでは、引き続き、雇用保険法の改正について見ていきましょう。
雇用保険法の改正について

上記「育児介護休業法」の改正とあわせ、「雇用保険法」についても「出生後休業支援給付金制度」創設による、産後一定期間の育児休業給付金支給率「実質100%」への引き上げや、「育児短時間勤務期間中」の賃金低下を補う給付金制度の創設等を盛り込んだ改正法が公布されました。
また、令和10年10月1日を制度施行日として、雇用保険の適用対象を拡大することも決定されています。
出生後休業支援給付の創設 ~産後一定期間の育児休業給付金支給率を実質100%へ引き上げ(令和7年4月1日 施行)
「産後の一定期間」において、両親共に14日以上の育児休業等を取得した場合は、両親それぞれへの給付について「給付率67%の(出生時)育児休業給付金」に上乗せが行われます。
(配偶者が育休対象者でない場合等、特定の事情がある場合は、片親のみ14日以上の育休取得でも支給されます)
28日間を限度に「給付率13%の出生後休業支援給付」を支給し、給付率を合計80%へ引き上げする内容となっています。
上記の新たな給付金が上乗せ支給される期間は、社会保険料控除も加味した場合、「実質100%」の手取り補償が行われることとなります。
上記の「産後の一定期間」については・・・
男性または養親である労働者の場合は、子の「出生日・出産予定日の早い方の日」~「出生日・出産予定日の遅い方の日の翌日から8週間以内」
子を出産した女性労働者の場合は、子の「出生日・出産予定日の早い方の日」~「出生日・出産予定日の遅い方の日の翌日から16週間以内」
を指します。
「ひとり親の家庭」や「配偶者が就業していない」「配偶者がフリーランスで働いている」など、「配偶者が育児休業を取得していること」を支給要件として適用できない被保険者については、配偶者の育休取得は支給要件となりません。
なお、こちらの制度について詳しく知りたい方は、以下の記事をご参照下さい。
育児時短就業給付(育児短時間勤務期間中の賃金低下を補う給付金制度)の創設(令和7年4月1日 施行)
「育児短時間勤務」期間中の賃金低下を補うものとして「育児時短就業給付」が創設されることとなりました。
2歳未満の子を養育するために「育児短時間勤務制度」を利用した場合、「時短勤務中の賃金」の最大1割を補助する制度内容となっています。
「育児短時間勤務前」の賃金の1割ではなく、「育児短時間勤務期間中」に、実際に支払いを受けた賃金の1割である点がポイントです。
育児休業給付金「延長申請時」の要件厳格化(令和7年4月1日 施行)
子が1歳もしくは1歳6か月に到達した際、保育所等へ入園できず、育児休業の延長が行われた場合は、育児休業給付金の支給についても延長申請することができます。
その一方、本来は保育所等への入所意思が無いにも関わらず、育児休業給付金の延長受給を目的とし、入所希望倍率の高い保育所へ恣意的な申込(いわゆる落選ねらい)をすることが頻繁に行われ問題となってきました。
上記を踏まえ、令和7年4月1日以降は、育児休業給付金「延長申請時」の手続きが以下のとおり厳格化されます。
【厳格化される内容】
延長時の支給申請書に添付する書面は、現行は「入所保留通知書」のみとなっていますが・・・
- 本人の記載による「育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書」
- 保育所等へ入所申込を行った際の「利用申込書」の写し
についても新たに提出が求められるようになります。
なお、上記1の「申告書」には・・・
✅自宅または勤務先からの移動に30分以上かかる保育所を申し込んだ場合は、その理由
✅入所内定を辞退した場合は、その理由
の記載を求めることとなっています。
もともと入所保留となることを希望して申込した者は支給延長の対象から除外されることとなります。
雇用保険の適用対象拡大(令和10年10月1日施行)
現在、被保険者要件とされている「1週20時間以上」の就労基準を「1週10時間以上」に半減させ、雇用保険の適用対象者数を大幅に増加させることが決定しました。
ただし、この改正法施行日は、令和10年10月1日からとされています。
国民年金法の改正案について

国民年金法についても令和6年度の通常国会にて、以下の法案が可決されています。
育児休業期間中の国民年金保険料免除制度開始(令和8年10月1日施行)
令和8年10月1日より、フリーランス・自営業者等「国民年金1号被保険者」に対しても、育児休業期間中の国民年金保険料を全額免除とする制度が施行されます。
この免除制度は、育児休業取得の有無に関わらず「1歳になるまでの子を養育する父母全て」を対象とすることとされており、所得要件や休業要件は設定されません。
産前産後休業期間中4カ月間の社会保険料免除が適用されている母親については、当該免除期間に引き続く9カ月間を免除対象月とします。
免除対象月分については満額の基礎年金が保障されることとなります。
当事務所では、小規模企業でも産休・育休手続きを円滑に進められるよう・・・
産休・育休手続ナビゲーション+申請手続代行サービスを
顧問契約不要・安心の一括スポット料金でご提供しております。
メールのみで・・・
- お申込み(別途 書面の郵送が必要となります)
- 最新の産休・育休制度情報収集
- 産休・育休、各種事務手続のアウトソーシング
まで、一筆書きで完了させることができる画期的なサービス内容となっております。
あわせて・・・
- 育休関連助成金の申請サポート【事前手数料なし / 完全成果報酬制】
- 助成金サポートのみ お申込みもOK
にも対応しております。(東京しごと財団 働くパパママ育業応援奨励金 の併給申請サポートも可能です)
完全オンライン対応で、就業規則等改定~助成金(奨励金)申請代行まで個別にサポート致します。
- 産休・育休取得実績が乏しい小規模企業のご担当者様
- ご多忙につき、「情報収集の時間確保」が難しいご担当者様
- 業務中断せず、自分のペースで支援を受けたいご担当者様
から大変ご好評いただいております。
【全国47都道府県対応】
メールで気軽に支援が受けられる!
CLASSY. 2024年2月号に掲載されました。
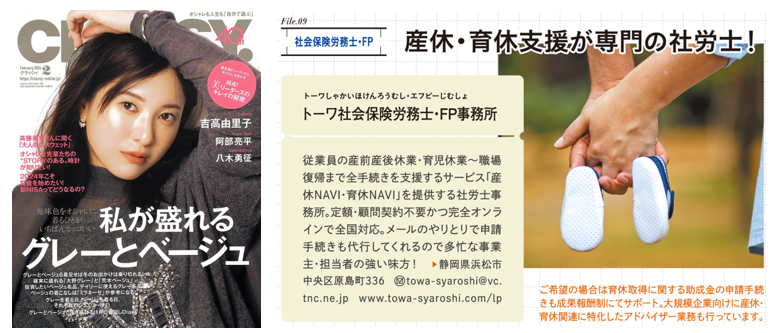
企業実務2025年2月号に寄稿しました。
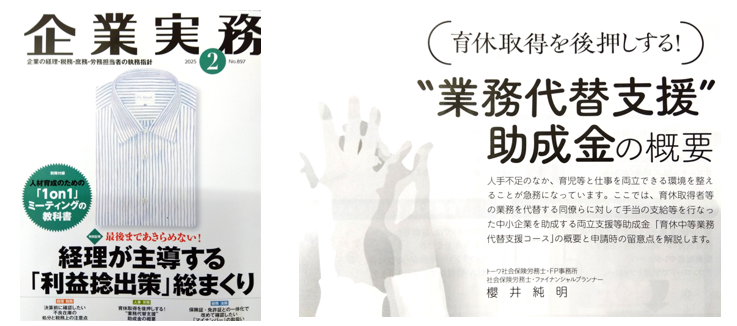
2025年4月「@Living」の取材に協力しました。

【両立支援等助成金・東京都奨励金 活用のご案内】
従業員の育休取得を推進する中小企業に対しては、非常に手厚い助成金・奨励金制度が設けられています!
育休関連の助成金・奨励金制度について知りたい方は、以下のサイトもご参照下さい。
欠員補充コストでお悩みの事業主様には、是非とも知っておいていただきたい内容となっています。
産休・育休関連情報 総合ページへのリンクはこちら!
以下のページからアクセスすれば、産休・育休関連の【各種制度・手続き情報】【最新の法改正情報】から【助成金関連情報】まで、当サイトにある全ての記事内容を閲覧することができます。

②.png)